俳句と世界平和

2022(令和4)年7月、欧州連合(EU)初代大統領で元ベルギー首相のヘルマン・ファンロンパイさんが、神奈川県鎌倉市で開催された俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会の総会に出席するために来日されました。
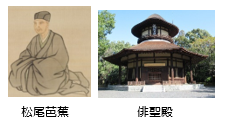
来日にあわせて、政治家としてのご経験をもとに「欧州の将来と日欧パートナーシップの行方~ウクライナにおける戦争、欧州そして世界への影響~」と題した講演をされましたが、ファンロンパイさんはオランダ語で俳句を詠み、これまでに2冊の句集を刊行され、「ハイク・ヘルマン」と呼ばれている俳人でもあります。
ファンロンパイさんは、「俳人は静かに注意深く対象を見つめる。平和はそんな態度を通じてこそ実現される」と語っておられます。俳句と平和との結びつきについては、長年、国際俳句交流協会会長を務められ、文部科学大臣としても活躍された、物理学者で俳人の故有馬朗人さんに出会い、その考えにとても共鳴されたとのことです。
有馬さんは、本市の岡本栄市長とともに「俳句のユネスコ登録を目指す発起人会」の呼びかけ人となり、その後のユネスコ登録運動をリードしてくださいました。有馬さんは、国際俳句交流協会の機関誌「H I」第126号誌上の「俳句で世界を平和に」と題した文章の中で、「俳句の主題は自然観察と日々の生活の中にあります。俳句は瞬間を永遠のものにすることが可能です。身近な自然を観察することは自然保護の心にもつながり、人々の相互理解を生み、ひいては世界の平和へとつながることになるのです」と、「俳句の平和性」について語っておられます。
世界で一番短い詩である俳句は、日本の伝統文学であるのみならず、世界の多くの国でそれぞれの言語で楽しまれています。
有馬さんは、「俳句を通して私たちは世界とつながっています。」とおっしゃいました。
ファンロンパイさんもまた、「俳句は調和を大切にしている。ねたみや欲、対立とは相いれません」とおっしゃっています。
戦争は、最大の環境破壊でもあります。俳聖芭蕉のふるさとに住む私たちは、俳句を通して平和な世界を実現し、世界の人々とともに環境を守っていかなくてはなりません。芭蕉自身もふるさと伊賀の風景を愛し、次のような句を詠んでいます。

『詠(ながむ)るや 江戸(えど)にはまれな 山(やま)の月(つき)』
芭蕉が江戸から伊賀へ里帰りした時の句です。平野の広がる江戸からは見ることのできない山の端から昇る月を、ふるさとで感慨深く眺めている様子が詠まれています。
そして、今も変わらず、私たちは、伊賀の山の端から昇る月を、芭蕉と同じように見上げています。きっと、その月を、地球の反対側の国の人たちも毎日眺めていることでしょう。
地球温暖化をはじめとして、環境問題は人間の引いた国境線に関係なく、世界中の人々とともに取り組まなければならない課題となっています。一人ひとりができることは小さな努力かもしれませんが、世界一短い俳句が世界とつながっているように、その小さな努力の積み重なりが、月明かりのように世界中の夜道を照らすことを願わずにはいられません。

